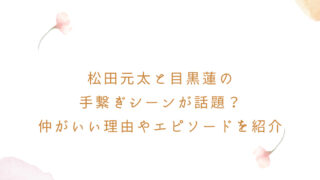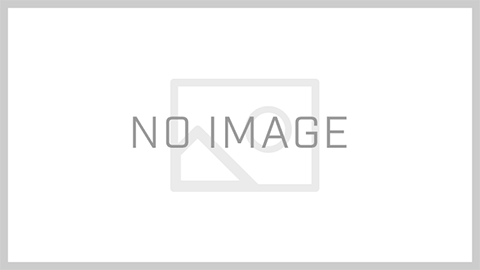彼岸の入り日は1年に2回春と秋にありますが、
- 彼岸の入り日とは何をする日なの?
- 彼岸の入り日はいつからなの?
- お彼岸のお供え物は何がいいの?
このような疑問があるのではないでしょうか。
この記事では彼岸の入り日について詳しく解説していくので、彼岸の入り日についての疑問は解消されるはずです。
目次
彼岸の入りの日とは何をする日なの?
彼岸入りの日とはいったい何をする日なのでしょうか?
そもそも「彼岸の入り日」とはお彼岸に入る日のことをいいますが、実は「彼岸入りの日」や「お彼岸」に何をするのかは決まっていないんです。
「えっ?お彼岸にすることってきちんと決まってるんじゃないの?」と思った人は多いはずです。
お彼岸って毎年ある行事なので、何をするのか決まっていないって意外ですよね。
彼岸の入り日にみんなは何をしているの?
でも彼岸の入り日やお彼岸には、お墓参りや仏具の掃除をするという風習や文化がありますよね。
特に一番初めに思い浮かぶのが「お墓参り」じゃないでしょうか。
普段あまり行けないので、お彼岸には必ずご先祖さまのお墓にお参りに行くという人も多いのではないかと思います。
普段行けない分、お墓の掃除や手入れに時間をかけたいところですよね。
ただお彼岸のいつお墓参りに行くか、日にちや時間が決まっているわけではありません。
でもお彼岸の期間はお寺や霊園が混んでいるんですよね。なので、少しでも早めに行くことをおすすめします。
他にも、ご家庭にある仏具などの掃除やお手入れにも時間をかけてキレイにするのがいいでしょう。
お彼岸の由来とは?
最近では「お彼岸」や「彼岸の入り日」という言葉自体を知らない人もいるかもしれませんが、由来について解説します。
ただ、知らず知らず3月や9月にお墓参りだけは参加しているという人もいるでしょう。
そもそも、お彼岸は日本だけで行われている行事なんです。
もともとお彼岸はインドから伝わった言葉で、「悟りの境地」という意味があるんだとか。
お彼岸の由来の1つとして、仏教発祥の地で有名なインドの言葉で「パーラミター」という言葉があります。
これは「到彼岸」という言葉なんだそうですが、「修行を積むことで煩悩(ぼんのう)を離れ悟りの境地に到達する」という意味があるそうです。
今の日本で使われている「お彼岸」はご先祖さまの供養として使われることが多く、お彼岸にお墓参りをするのは日本だけの文化なんですね。
お彼岸の日が春と秋にあるのはなぜ?
お彼岸の日は、なぜ春と秋の1年に2回あるのでしょうか?
これは春分の日と秋分の日の違いがあり、
- 春分の日は「自然をたたえ、生物をいつくしむ」という目的
- 秋分の日は「祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ」という目的
こんな目的があったんですね。
でも春のお彼岸も秋のお彼岸も、ご先祖さまの供養の仕方は同じです。1年に2回、同じように供養をするのがいいでしょう。

彼岸の入り日にお供えするお菓子は何がいい?
彼岸の入り日にお供えするお菓子は何がいいのでしょうか?
よく彼岸の入り日に使われているのは「ぼたもち」と「おはぎ」です。

「あれ?ぼたもちとおはぎって同じじゃないの?」って思ったんじゃないでしょうか。
そうです。たしかに同じものなんです。でも春は「ぼたもち」に、秋は「おはぎ」に名前が変わるんです。
実はその季節に咲く花によって名前が変わっているんですが、
- 春は「牡丹(ぼたん)の花」からとって「ぼたもち」
- 秋は「萩(はぎ)の花」からとって「おはぎ」
となったと言われています。
その季節に咲く花によって名前が変わるなんて、おもしろい食べ物ですね。
お彼岸に「ぼたもち」や「おはぎ」をお供えする理由
ぼたもちやおはぎに使われている材料は「あずき」ですよね。
このあずきの赤色は「魔よけ」の意味があるそうなんです。なので、悪いものを入ってこないようにする意味込めているんだとか。
彼岸の入り日には、和菓子やくだものをお供えするのもいいでしょう。他にはご先祖さまが好きだったものをお供えするのもいいですね。
彼岸の入り日にお供えする花は何がいい?
彼岸の入り日にお供えする花には
- とげのある花
- においの強い花
- 毒のある花
などは使わないように気をつけましょう。
お墓参りに使われることが多いので、日持ちする「菊の花」がよく選ばれています。

彼岸の入り日に花を贈るとき
花を贈る場合は、彼岸の入り日の午前中くらいまでには届くようにしましょう。遅くとも中日(春分の日・秋分の日)までには届けるのが一般的です。
届けるのは花束かフラワーアレンジメントで、花屋さんに「お彼岸用」とお願いするのがいいでしょうね。
彼岸の入り日はいつから?
彼岸入りの日がいつからなのかというと、
3月は「春分の日を真ん中にして前に3日、後に3日の合計7日間」が春のお彼岸の期間なんです。
なので、春の彼岸の入り日は「春分の日の3日前」となります。
同じように、9月は「秋分の日を真ん中にして前に3日、後に3日の合計7日間」が秋のお彼岸の期間です。
つまり、秋の彼岸の入り日は「秋分の日の3日前」なんですね。
春分の日や秋分の日は、国立天文台がつくる暦象年表をもとに閣議で決められています。
なので、彼岸の入り日は「何月何日」と日付で決まっているわけではないんです。
彼岸の入り日とは何をする日でいつから?お供え物や由来について調査まとめ
彼岸の入り日について解説してきましたが、
- 「彼岸の入り日」や「お彼岸の日」に何をするかは決まっていないが、風習や文化としてお墓参りや仏具の掃除をする
- 彼岸の入り日は「春は春分の日の3日前」で「秋は秋分の日の3日前」
- お彼岸のお供え物は、春は牡丹の花からとって「ぼたもち」で、秋は萩の花からとって「おはぎ」を備えるのが一般的
彼岸の入り日には家族でご先祖さまの話をしたり、感謝の気持ちを伝えあったりするのがいいでしょう。