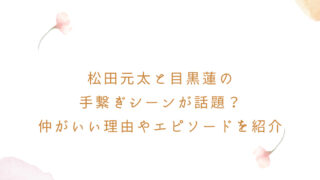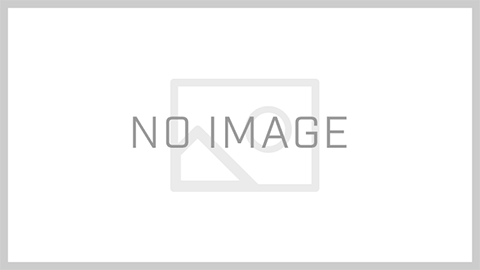勤労感謝の日といえば11月23日ですが、祝日なので仕事が休みの家庭も多いですよね。
では子供に「勤労感謝の日って何?」と聞かれたとき、きちんと答えることができますか?
そこで今回は、勤労感謝の日とはいつできたのか?子供向けに簡単に由来や意味を説明できるように詳しく書いていきます。
目次
勤労感謝の日はいつできたの?
勤労感謝の日は、昭和23年にできた祝日です。
それまでは新嘗祭(にいなめさい)という収穫祭だったんですが、この収穫祭が勤労感謝の日として制定されたのが始まりなんです。
勤労感謝の日とは?子供向けに簡単に説明してみよう
勤労感謝の日がどんな日なのか、正確にはむずかしい言葉で書かれています。それがこちら。
「勤労をたっとび、生産を祝い、国民たがいに感謝しあう。」
なんとも難しく書かれていますよね。そこで子供向けに簡単に説明するにはどう伝えればいいか考えてみました。
まず意識するのは子供にわかりやすい言葉を使うことです。
- 勤労は「お仕事」
- 感謝は「ありがとう」
- 生産は「作っている」
こんな風にわかりやすく言い換えた言葉を使ってあげると、子供にも伝わりやすいはずです。
勤労感謝の日を子供に簡単に説明するには?
例えば1つの例として、勤労感謝の日をこのように伝えてみてはどうでしょうか。
今食べているご飯は、農家のおじさんが一生懸命働いてお米を作ってくれたから美味しく食べられるんだよ。
そしてお父さんやお母さんは、そのお米を買うために一生懸命働いているの。
勤労感謝の日は、農家のおじさんやお父さんお母さんみたいに、食べ物を作る人やそれを買うために働く人たちみんなにありがとうを伝える日なんだよ。
このように作る人・買う人みんなが働くことによって、みんなが幸せになるということ。そして「お互いに感謝することが大切」と伝えることを意識するといいと思います。
勤労感謝の日の由来や意味は?
新嘗祭(にいなめさい)はあまり聞き慣れないかもしれませんが、実はこの新嘗祭が勤労感謝の日の由来と言われているんです。
というのも、新嘗祭とはその年の収穫を神様に感謝する日で、勤労感謝の日ができるまでは収穫祭として行われていました。
今も新嘗祭は11月23日に行われています。
勤労感謝の日の由来になった新嘗祭って何?
新嘗祭(にいなめさい)は天皇が国民を代表して神様に1年の収穫を感謝し、国民は収穫した食べ物を作っている人たちに感謝を伝えましょうという儀式なんです。
とはいえ、いまでは農作物に限らず作っているものは色々あるので、新嘗祭自体にはあまり馴染みがないかもしれません。
でも子供に説明するためには知っておいた方が、勤労感謝の日を説明しやすいと思います。
収穫祭が勤労感謝の日として制定されたのが始まりですが、今では農作物に限らず生産を祝って、働く人や働くことに感謝する日として広まっています。
勤労感謝の日とはいつできた?子供向けに簡単に由来や意味を説明!まとめ
勤労感謝の日について書いてきましたが、子供にとってだけでなく実は大人にとってもわかりにくかったかもしれません。
ただ、作った人や買う人などの働く人や働くことに感謝する日ということはしっかり伝えてほしいと思います。